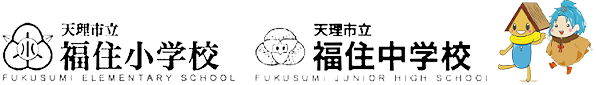狂言体験
2日(水)3・4時間目にG7~9が狂言体験をしました。
森山泰幸さんと能楽師3名と狂言師2名の方々が来校してくださいました。
狂言で使われる楽器の説明をしていただきました。
【能管(のうかん)】
【小鼓(こつづみ)】
【大鼓(おおつづみ)】
狂言とは、滑稽な喜劇なのですと教えていただきました。
だから狂言鑑賞するときには、
①想像力をかき立てて見る
②喜劇なので軽い気持ちで楽しんで見る
③みんなで役者をもり立てる(役者と鑑賞者の意思の疎通をはかる)
この3つが大切と教えていただきました。
扇子の使い方も教えていただきました。
これは何をしているのでしょうか?(想像力をはたらかして)
答えは、『お酒を飲んでいるところ』です。
狂言の笑いは、『小(こ)笑い』『中(ちゅう)笑い』『大(おお)笑い』の3つがあることを教えていただき、
『大笑い』のやり方(エスカレーターのように声の高さを上げて、8回に切り分けてどんどん声の高さを下げていく)をみんなで練習しました。
楽器体験では、小鼓と大鼓を使って音を出す練習をしました。
【小鼓】
【大鼓】
最後に『寝音曲(ねおんぎょく)』を鑑賞しました。
みんな狂言鑑賞するときの3つのポイントを意識して鑑賞できました。
森山泰幸さん、能楽師さん、狂言師さん、日本の伝統文化の狂言を身近に感じさせていただき、本当にありがとうございました。